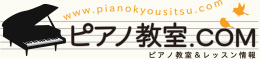新しい曲に入ったら…②
今日は前回の続き。
新しい曲の練習をスタートする際、
「やる気」と「嬉しさ」のあまり、楽譜を広げて、
いきなり、ドミソファ…と弾き始めちゃう人っていると思うけど、
それ、ちょっと待って!新しい曲を弾き始める前に、
まず、やって頂きたいことが「4つ」あるんですよ~。
…というお話を書きました。
1・楽譜全体(曲全体)を把握する。(何となくでOK)
2・曲調を理解する。(#♭をチェック)
3・拍子やテンポを理解する。(何分の何拍子?)
4・知っている曲や、メロディーラインがはっきりしている曲なら
楽譜を目で追いながら鼻歌を歌ってみる
前回、1に関しての説明をしたので、
今日は、「2・曲調を理解する」について書きますね。
_______________________
まず。
何調なのか確認せずに弾き始めてしまう人は、
その曲が明るい曲調なのか、暗い曲調なのか、
わからないまま弾いている、という事が多々あります。
これでは、『曲の全体をイメージする』という大事な作業ができません。
(イメージする事の大切さは前回の記事に書いています)
「#も♭も無いからハ長調。だから明るい曲に決まってるもんね!」
と、思ったアナタ!危険ですよ~。
イ短調(暗い感じの曲調)っていう場合もあるんです。
また、その曲に#や♭の調号がある場合、
きちんとチェックせず弾き始めるというのは、
「どの音を#(または♭)するのかわかっていない」
ということですよね。
つまり、これ、間違った音を鳴らしながら
練習を進めてしまっている可能性大!(汗)
「何だか変なメロディーだな~」と感じたら、要注意!
上記の2つのことから、「この曲は何調なのか?」
理解してから練習(譜読み)に入ることは、非常に大事なんです。
新しい曲の譜面を開いたら、まず、ざっと全体に目を通し(←1の作業)、
自分なりに「こんな感じかな?」と分析&イメージします。
その後、調号がついているかどうかをチェック。(←2の作業)
「え~っと、シの所に♭がついているな…」
初心者さんはこれでOK。
実際に音を鳴らしながら譜読みを進める際、
「シの音が出てきたら半音下げる」
↑これを忘れないようにしましょう♪
「え~っと、シの所に♭がついている。 ということは…
ヘ長調(F Major scale)か、ニ短調(D minor scale)だな。
さて、この曲はどっちだろ?」
こんな風に、曲調まで考えられるようになったら素晴らしいですね~。
曲のイメージもグっと膨らみます。
簡単な音楽理論を勉強するだけで、
誰でも調号から調を把握できるようになります。
初心者さんの場合、「弾くことで精一杯だし理論どころじゃない!」
という方も多いですが、少しずつ理解できるよう、
レッスンの際には新しい曲に入るたびに、
何度でも丁寧に説明しますので、安心してくださいね。
また、新しい曲のレッスンに入る際、私がいつもピアノを使ってする
『スタートの音探し』も、曲調を把握するのには簡単方法なのでオススメ。
「理論は難しそうだから…」という方は、
是非、『スタートの音探し』をご自分でやってみて、
音階のスタートの音(主音)を探してから、譜読みに取り組みましょう~。
※『スタートの音探し』?なんだそりゃ?
と言う方は、レッスンの際に質問してください。
そして、ある程度指が動き、ピアノが弾ける方は、
新しい曲を譜読み&弾き始める前に、
その調のスケール(音階)を、一通り弾いてみましょう。
できればカデンツァ部分まで弾けるといいですね。
こうすることで、より一層、曲の雰囲気が掴みやすくなりますし、
カデンツァを鳴らすことで、主要な和音を、予め指で確認することができるし、
よくある和音の流れ(Ⅴ-Ⅰなど)も把握できるので、
譜読みを進める際、実際に役立つことも多いです。
今日、説明した「2」の作業、難しそう?面倒くさそう?
どうぞご安心を~。
慣れて(理解して)しまえば何の苦労もいらない作業です!(キッパリ)
新しい曲に入ったら、毎回、「調号をチェックし、曲調を確認する」
皆さん、癖付けてしまいましょう~♪
新しい曲の練習をスタートする際、
「やる気」と「嬉しさ」のあまり、楽譜を広げて、
いきなり、ドミソファ…と弾き始めちゃう人っていると思うけど、
それ、ちょっと待って!新しい曲を弾き始める前に、
まず、やって頂きたいことが「4つ」あるんですよ~。
…というお話を書きました。
1・楽譜全体(曲全体)を把握する。(何となくでOK)
2・曲調を理解する。(#♭をチェック)
3・拍子やテンポを理解する。(何分の何拍子?)
4・知っている曲や、メロディーラインがはっきりしている曲なら
楽譜を目で追いながら鼻歌を歌ってみる
前回、1に関しての説明をしたので、
今日は、「2・曲調を理解する」について書きますね。
_______________________
まず。
何調なのか確認せずに弾き始めてしまう人は、
その曲が明るい曲調なのか、暗い曲調なのか、
わからないまま弾いている、という事が多々あります。
これでは、『曲の全体をイメージする』という大事な作業ができません。
(イメージする事の大切さは前回の記事に書いています)
「#も♭も無いからハ長調。だから明るい曲に決まってるもんね!」
と、思ったアナタ!危険ですよ~。
イ短調(暗い感じの曲調)っていう場合もあるんです。
また、その曲に#や♭の調号がある場合、
きちんとチェックせず弾き始めるというのは、
「どの音を#(または♭)するのかわかっていない」
ということですよね。
つまり、これ、間違った音を鳴らしながら
練習を進めてしまっている可能性大!(汗)
「何だか変なメロディーだな~」と感じたら、要注意!
上記の2つのことから、「この曲は何調なのか?」
理解してから練習(譜読み)に入ることは、非常に大事なんです。
新しい曲の譜面を開いたら、まず、ざっと全体に目を通し(←1の作業)、
自分なりに「こんな感じかな?」と分析&イメージします。
その後、調号がついているかどうかをチェック。(←2の作業)
「え~っと、シの所に♭がついているな…」
初心者さんはこれでOK。
実際に音を鳴らしながら譜読みを進める際、
「シの音が出てきたら半音下げる」
↑これを忘れないようにしましょう♪
「え~っと、シの所に♭がついている。 ということは…
ヘ長調(F Major scale)か、ニ短調(D minor scale)だな。
さて、この曲はどっちだろ?」
こんな風に、曲調まで考えられるようになったら素晴らしいですね~。
曲のイメージもグっと膨らみます。
簡単な音楽理論を勉強するだけで、
誰でも調号から調を把握できるようになります。
初心者さんの場合、「弾くことで精一杯だし理論どころじゃない!」
という方も多いですが、少しずつ理解できるよう、
レッスンの際には新しい曲に入るたびに、
何度でも丁寧に説明しますので、安心してくださいね。
また、新しい曲のレッスンに入る際、私がいつもピアノを使ってする
『スタートの音探し』も、曲調を把握するのには簡単方法なのでオススメ。
「理論は難しそうだから…」という方は、
是非、『スタートの音探し』をご自分でやってみて、
音階のスタートの音(主音)を探してから、譜読みに取り組みましょう~。
※『スタートの音探し』?なんだそりゃ?
と言う方は、レッスンの際に質問してください。
そして、ある程度指が動き、ピアノが弾ける方は、
新しい曲を譜読み&弾き始める前に、
その調のスケール(音階)を、一通り弾いてみましょう。
できればカデンツァ部分まで弾けるといいですね。
こうすることで、より一層、曲の雰囲気が掴みやすくなりますし、
カデンツァを鳴らすことで、主要な和音を、予め指で確認することができるし、
よくある和音の流れ(Ⅴ-Ⅰなど)も把握できるので、
譜読みを進める際、実際に役立つことも多いです。
今日、説明した「2」の作業、難しそう?面倒くさそう?
どうぞご安心を~。
慣れて(理解して)しまえば何の苦労もいらない作業です!(キッパリ)
新しい曲に入ったら、毎回、「調号をチェックし、曲調を確認する」
皆さん、癖付けてしまいましょう~♪
このブログへのコメント