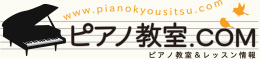小学生のアナリーゼワーク①(夏休みの自由研究レッスンより)
小学生の楽曲分析のワークを
夏休みに開催したことがありました。
分析というと~どんなことを思い浮かべる?
と聞くと
少し弾けるような生徒さんは
楽典の初歩などをやっているため、
「形式」とか「和音」という言葉が出ます。
それは~すぐ見つかるよね。
でも、
そうした‘見た目’ではなくて
自分で考えながら曲を深く読譜する習慣をつけて欲しいな
と思います。
同じメロディーなのに、
違う和音がついている!
そんなことが見つかった生徒さんもいます。
「見つけた!」
だけではなくて~~
じゃあなぜ、ココとココの和音が違うんだろう?
和音の違いにどんなニュアンスがあるんだろう?
なぜ、反対ではないんだろう?
そうすると
和音そのものの「働き」「次への誘い方」に
違いがあることがわかります。
じゃあ~同じような使われ方がしてある曲は
どんなものがあるだろう?
ならば、その部分はどんな演奏が求められているだろう?
あなたはどう思う?
そんな考え方を楽譜を目の前にして
できるようになると、
音楽が深く味わえるようになります。
皆さんににメロディーを書いてもらって
私が何種類かの和音伴奏をつけてみますと~
「オ~!」
とか
「思ったよりきれい」
とか
「かっこよくなった」
とか・・・。
和音ひとつでも全然感じが変わることを
自ら体験!
自分でもさぐってゆけたら楽しいよね?
前説を読んで
こんな形式らしいね。
こんな風にできてるらしいね~~
って・・・
わかった気になってしまう?
それで終わるなんてもったいない!
それが100%??
本当かな?
って思う目も音楽には必要です。
私はどう思う・・・が。
そこから発展してゆくさまざまなことがあります。
ポリフォニックな曲では
実際に簡単なカノン作成をしてみよう!と・・・。
たった2声の四分音符の4小節のカノンを作ることの
なんとむずかしいことか!
ヒント満載にして
頭をひねりながら~~
当時ピアノコンクールの常連だった小学生の男の子の生徒さんが
うなりながら~楽しそうな笑顔を見せてくれたのが印象的でした。
夏休みに開催したことがありました。
分析というと~どんなことを思い浮かべる?
と聞くと
少し弾けるような生徒さんは
楽典の初歩などをやっているため、
「形式」とか「和音」という言葉が出ます。
それは~すぐ見つかるよね。
でも、
そうした‘見た目’ではなくて
自分で考えながら曲を深く読譜する習慣をつけて欲しいな
と思います。
同じメロディーなのに、
違う和音がついている!
そんなことが見つかった生徒さんもいます。
「見つけた!」
だけではなくて~~
じゃあなぜ、ココとココの和音が違うんだろう?
和音の違いにどんなニュアンスがあるんだろう?
なぜ、反対ではないんだろう?
そうすると
和音そのものの「働き」「次への誘い方」に
違いがあることがわかります。
じゃあ~同じような使われ方がしてある曲は
どんなものがあるだろう?
ならば、その部分はどんな演奏が求められているだろう?
あなたはどう思う?
そんな考え方を楽譜を目の前にして
できるようになると、
音楽が深く味わえるようになります。
皆さんににメロディーを書いてもらって
私が何種類かの和音伴奏をつけてみますと~
「オ~!」
とか
「思ったよりきれい」
とか
「かっこよくなった」
とか・・・。
和音ひとつでも全然感じが変わることを
自ら体験!
自分でもさぐってゆけたら楽しいよね?
前説を読んで
こんな形式らしいね。
こんな風にできてるらしいね~~
って・・・
わかった気になってしまう?
それで終わるなんてもったいない!
それが100%??
本当かな?
って思う目も音楽には必要です。
私はどう思う・・・が。
そこから発展してゆくさまざまなことがあります。
ポリフォニックな曲では
実際に簡単なカノン作成をしてみよう!と・・・。
たった2声の四分音符の4小節のカノンを作ることの
なんとむずかしいことか!
ヒント満載にして
頭をひねりながら~~
当時ピアノコンクールの常連だった小学生の男の子の生徒さんが
うなりながら~楽しそうな笑顔を見せてくれたのが印象的でした。
このブログへのコメント